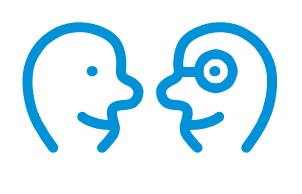「先祖代々続いてきた家業を、私の次の者に継いでもらいたい」
「私が苦労して築いたこの事業、私が引退後も継続してもらえたら」
と考えている、中小企業の社長や、個人事業主の皆さん(以下、社長等と記します)。
ご自身の終活に加えて、事業を円滑に受け継いでもらうために「事業継続用の終活」が必要になります。

この事業継続用の終活の主なメニューは次のような事項になります。

- 後継者候補の決定
- 事業承継計画
- 遺言書の作成
- 遺留分への対応
- 贈与税・相続税等への対策
事業を円滑に継承するための支援制度もあります。支援制度の内容や利用の可否を検討することも社長等の終活の一つです。

事業継続用の終活には時間がかかります。後継者が見つかってから実際に後継者に引き継ぐまでに、少なくとも3年はかかるという調査結果もあるようです。
ですから、元気なうちに準備に取り掛かりましょう。
Table of Contents
1.後継候補の決定
事業や会社経営の後継者として、次の3つの類型から候補者を選定することになります。
| A 親族 | 子、孫、甥姪、従兄弟姉妹やその子、子や孫等の配偶者などの「身内」 |
| B 役員・従業員 | 共同経営者、会社の役員、従業員 |
| C 第3者 | 上記のAやB以外の人、法人 |
第3者から後継者を探す場合、社長等の努力で見つからない場合があります。
そうした場合には、地元の自治体、取引している金融機関の他、次のサイトに登録している仲介業者に相談してみると良いかもしれません。
それでも後継者が見つからない時。
残念ではありますが、廃業の時期を決め、準備を開始した方が良いかもしれません。
仮に「死ぬまで事業を続ける」という場合でも、ご遺族が亡くなった後の事業の後始末が行えるように準備をしておくべきです。
2.事業承継計画
後継者の候補が見つかったら、事業承継計画を候補者と相談しながら立てた方が良いでしょう。
事業の内容や方法の伝達、取引先との関係の維持、権限の段階的な移譲、社長が会社の事業資金の融資の保証人になっている場合への対応など計画的に行った方が後継者も事業承継に見通しと主体性を持って取り組めるようになるからです。
また、事業承継の足かせとなるような事柄への対応を支援する様々な制度があります。
これらの事業承継を支援する制度を受けるためには、いくつかの条件を満たしていることが前提であることが多いです。例えば、後継者に会社の株を贈与する場合、贈与税の特例を受ける後継者の条件に「株を贈与する直前、その会社の役員であった」のような条件が付されていることがあります。
どのような支援制度があり、利用する際の条件は何なのかということも踏まえて事業承継計画を立て準備した方が良いでしょう。
また、事業承継計画の策定それ自体が、支援を受ける前提になっている場合もあります。
3.遺言書

所有している店舗・事務所・工場などの不動産や、会社の株・持分を後継者に譲り渡す必要がある場合。生前に贈与できれば良いですが、何らかの事情で贈与できない、あるいは贈与しない場合もあるでしょう。
そうした場合に備えて高齢の社長等は遺言書を作成しておくべきです。
遺言書は何度でも書き換えることができるので、事業用の資産をすべて手放したら、それに合わせて遺言書を書き換えれば良いでしょう。
※事業用の不動産を後継者に譲り渡すのではなく、賃貸することもあるかもしれません。この場合、不動産と賃貸人としての地位を相続人に相続させる方法と、民事信託を利用する方法が考えられます。
4.遺留分への対応

遺言によって、店舗等の不動産や会社の株などの事業用の資産を後継者に遺贈する場合、もしかすると後継者以外の相続人の遺留分を侵害するかもしれません。というより、侵害することの方が普通でしょう。
遺留分を侵害された相続人は、遺産を受け継いだ他の人に遺留分に足りない金額を請求することができます。
そうすると、後継者が遺留分を請求される可能性が高いため、事前にその対策を準備しておくべきです。
対策としては、次の3つの方法があります。
- 予想される遺留分侵害額を準備する。
- 社長等が元気なうちに、配偶者や子に遺留分の放棄をしてもらう。
- 遺留分の計算をする時に、事業用の資産は含めないという合意書を作成する。
この方法については、別のページで改めて説明します。
遺留分とは
配偶者と子※に認められている最低限度の相続分のことを遺留分と言います。
遺留分は、「法定相続分の2分の1」です。
実際に相続した価額が、遺留分に足りない場合は(このことを「遺留分の侵害」と言います)、その足りない分を、他の遺産を受け継いだ人に請求することができます。
※子が遺言者より先に死亡している場合には、その死亡した子の子、つまり遺言者の孫が相続人になります
※子も孫もいない場合には、遺言者の親が相続人になり、親にも遺留分が認められています。
※親もいない場合には、遺言者の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の放棄
遺留分の放棄は、相続の放棄とは違い、相続をすることは可能です。「法で認められている相続分より少なくとも文句は言いません」という意思表示だと考えれば良いでしょう。
一方で注意が必要なのは、遺留分の放棄は相続すること自体は可能なので、債務も相続するし、相続分に応じて相続税等の負担が生じることもあり得ます。
「債務も含めてすべての遺産を相続しない」という場合には、相続放棄を家庭裁判所に申立てます。
遺留分の放棄は、遺言者が生きている時だけでなく、死後にすることもできます。死後に遺留分の放棄をする場合には、法律上の手続は必要ありません。遺言書に従うだけでOKです。
5.贈与税、相続税等への対策
社長等が生存中に、後継者に事業用の資産や会社の株式を贈与する場合には、贈与税への対応が必要になります。
社長等が亡くなった後に、後継者に資産を等を譲る場合には、相続税への対応になります。
事業の承継がスムーズに進むように、贈与税や相続税の特例を利用しましょう。
ものすごく簡単に言えば、この特例を利用すると贈与税や相続税の納税の猶予を受けられます。
また、承継した事業継続中に贈与した社長等が亡くなった場合には、猶予されていた納税額の全部または一部が免除されます。
一方で、承継した事業をやめたり他の人に譲り渡した場合には納税猶予が終わり、贈与税を納付するようになるので注意しましょう。
この特例は「法人版事業承継税制」という会社に適用できる特例と、「個人版事業承継税制」という個人事業に適用する特例に分かれます。
法人・個人のどちらの事業承継税制を受けるにも、次の段階を経る必要があります。
<贈与で事業用の資産を受け継ぐ場合>
①事業承継計画を策定
②事業承継計画に認定経営革新等支援機関による所見を記載してもらう
③令和8年3月31日まで*に事業承継計画を都道府県知事に確認してもらう
④事業用資産の後継者への贈与
⑤社長等と後継者が、この特例を受けるための要件を満たしていることを都道府県知事に認定してもらう
⑥贈与税の申告期限までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告 と 贈与税の納税の猶予を受けるための担保の提供
<相続で事業用の資産を受け継ぐ場合>
手続の手順は上の「贈与で事業用の資産を受け継ぐ場合」と同じです。
違いは④が「贈与」ではなく、「相続」になることです。また、⑥が「贈与税の申告」ではなく「相続税の申告」になる点です。申告期限も異なることにも注意してください。
6.その他
実際に後継者が事業を承継した後、売上高が落ちたり、事業用資産を受け継ぐ代わりに他の相続人に代償金を支払わなければならないかもしれません。
こうした資金を金融機関や日本政策金融公庫*から融資してもらいやすくするための支援制度があります。
株式会社で所在がわからない株主のために株主総会決議に支障がでる場合、会社法で株式会社が所在不明の株主の株式を売却(または会社が買い取る)規定があります。
通常の手続きだと、所在不明から5年を経過しないと売却までの手続きが取れませんが、社長の承継の目的なら1年間の所在不明なら手続きが開始できるという会社法の特例が利用できるかもしれません。
これらの金融支援制度や会社法の特例を利用するためには、都道府県知事の認定が必要です。
一人で考え込まず、一緒に対応を考える人を!
事業の承継は、多くの視点で考え、準備し、行動していく必要がありますが、 社長等が1人で考えて解決するのは難しいと思います。
まずは法や制度に詳しい者に相談しながら進めましょう!
ただ、1人の専門家が事業承継に関わる全ての事項に精通しているとも思えませんし、その専門家だけで全ての手続に対応できるものでもありません。
ある場面では認定支援機関が作成する書類が必要になり、別の制度では税理士等の確認が求められることもあります。不動産の登記や遺留分の放棄を家庭裁判所に申立てる場合には司法書士に依頼した方が良いかもしれません。
それでも最初の相談の窓口には行政書士が適していると、私は思います。
なぜなら、事業承継の支援制度は、経済産業大臣や都道府県知事の確認や認定を求めることが前提になっているものが多く、この業務を受任できるのは行政書士だからです。
他の専門家との連絡調整も行政書士が担います。ですから社長等はご自身にしかできない事に専念してください。