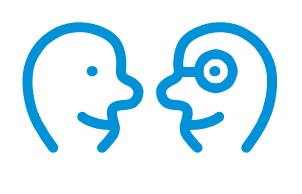事業を受け継いでもらいたい社長や個人事業主(以下、社長等と記します。)が、遺言に「事業用の資産を後継者に遺贈する*」旨を書いた場合、後継者以外の相続人の遺留分を侵害することがあると思います。
*遺贈というのは、「遺言を書いた人の財産の全部または一部を、亡くなった時に●●にあげます」という意味があります。
この場合、先代社長等が亡くなった後、遺言書に基づき遺産を承継する際に、後継者はたの相続人から「遺留分に足りない分」の支払いを請求される可能性があります。
そのため、社長等は後継者が安心して事業を継続できるように、あらかじめ対策を講じた方が良いでしょう。
対策としては、次の3つの方法があります。
- 予想される遺留分侵害額に相当する金銭を準備する。
- 社長等が元気なうちに、配偶者や子に遺留分の放棄をしてもらう。
- 遺留分の計算をする時に、「事業用の資産は含めない」等の内容の合意書を作成する。
このページでは、上の3つの方法について簡単に説明いたします。
Table of Contents
1.予想される遺留分侵害額を準備する
実際に相続した価額が遺留分に足りない場合、その不足分を遺留分侵害額と言います。
相続人は遺留分侵害額を金銭で支払うように後継者等に請求する権利があり、請求された後継者は金銭で支払う義務が生じます。
その支払に充てる金額を後継者が工面できるようにする方法ですが、次のような方法が考えられます。
ただ、いずれも準備できる金額が遺留分侵害額を支払うには足りなくなることも有り得るので、いくつかの方法を組み合わせた方が良いでしょう。
①生前贈与で渡す方法
生前贈与の非課税枠などを利用して後継者に金銭を渡す方法です。
ただ、遺留分や相続税の計算には生前贈与の金額も含まれてしまうものもあるのが欠点です。
②生命保険の死亡保険金の受取人を後継者にする方法
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産であり、基本的には相続財産には含まれません。そのため、遺留分侵害額への対策に生命保険の利用価値は高いと言えます。
ただ欠点がないわけではありません。
後継者が社長等の法定相続人であれば、相続税の計算時に死亡保険金から「500万円×相続人の数」だけ控除できますが、後継者が相続人でなければこの控除はできません。つまり、相続税負担が増える可能性があります。
そもそも死亡保険金の受取人に指名できる人が生命保険の約款で決められているため、場合によっては後継者を受取人に指名できないこともあり得ます。また、遺留分侵害額の全額を死亡保険金でまかなえないことも考えられます。
さらに、生命保険の契約の仕方によっては、相続税ではなく後継者に所得税又は贈与税が課せられる可能性もあります。
③先代の社長等が亡くなった後、後継者が経営承継円滑化法に基づく金融支援を受ける方法
これは後継者が先代の社長等が亡くなった後に事業を承継した場合に、遺留分侵害額の請求に基づいて支払う金銭の額を、日本政策金融公庫(又は沖縄振興開発金融公庫)から融資を受けたり、金融機関からの借入に信用保証協会が債務保証を受けられるという制度です。
この制度を利用するには、都道府県知事の認定が必要になる他、様々な条件があります。
2.遺留分を放棄してもらう
後継者以外の相続人全員に遺留分を放棄してもらえれば、後継者は遺留分侵害額請求を考えることなく事業を承継できるでしょう。
遺留分の放棄とは、簡単に言えば「遺言書に書いてある通りの相続分で良いです」という意思表示です。
先代社長等が亡くなった後に遺留分の放棄をしてもらう場合には、法的な手続は特に必要はありません。ただ先代社長等が安心して後継者に事業を託す方法としては不確かさが大きいのでお勧めできかねます。
先代社長等が元気なうちに後継者以外の全ての相続人を説得して、遺留分の放棄をしてもらうこともできます。
この場合には、全ての相続人が、各自、家庭裁判所に遺留分の放棄を申立ててもらいます。そのため、後継者以外の相続人の全員が申立ててくれるかどうかが課題になります。
遺留分の放棄 と 相続放棄の違い
「遺留分の放棄」は「実際に相続する資産の価額が遺留分に満たなくても構いません」という意思表示なので、相続する事はできます。
ただし、先代社長等に負債があった場合には、債権者から支払いを求められる可能性があったり、相続分に応じた相続税等の負担がある可能性はあります。
一方の、家庭裁判所に申立ててする「相続放棄」は、「はじめから相続人ではない」という扱いになるので、相続分は無く、債権者からの支払い請求に応じる必要もなく、相続税の負担もありません。
家庭裁判所に申立てずに、「相続分は無い」という遺産分割協議書等への署名捺印でする実質的な相続放棄もあります。この方法の場合は、債権者からの債務の支払い請求はあり得ます。「相続分はありません」という主張を受け入れてくれる債権者なら良いのですが...。
3.遺留分の計算についての合意書
事業や会社の後継者のための遺留分対策として、当事務所が最もお勧めしたいのが、この合意書作成による方法です。
これは、次のAかBのどちらかの内容を含めた合意書を、推定相続人全員と後継者で作成する方法です。(AとBの内容を組み合わせることも可能です)
| A 除外合意 | 遺留分の計算する時に、後継者が先代社長等から贈与や相続で取得した会社の株式等*や事業用の資産を除外するという合意 |
| B 固定合意 | 遺留分の計算をする時に、後継者が取得した会社の株式等の価額を、合意した時の時価*に固定するという合意 |
*株式等とは、株式会社の株式、合同会社等の場合は持分のことです。
*会社の株式等の時価は、税理士や公認会計士、弁護士による証明が必要です。
個人事業の場合は、除外合意が合意内容になります。
後継者が会社の社長の場合は、「会社の株式等」が除外合意または固定合意の対象になります。事業用資産は対象になりません。なぜなら、会社の事業用資産は会社名義であるはずで、その価値は株式等の評価額に反映されているからです。
この合意書方式は、後継者以外の相続人が遺留分を放棄することでも相続を放棄することもありません。ただ、遺留分を計算する際の相続財産の総額が、通常の計算方法より少なくなるところに特徴があります。
合意書を有効にするために
合意書の効力を有効にするには、次のような手順を踏みます。
※次の手順を踏まずに、合意書作成だけで終わらせてしまうと、合意書は「内輪の申し合わせ事項」に止まり、後でトラブルの原因になりかねません。
(1)合意書の作成
まず、後継者と推定相続人全員で合意書を作成します。
このとき、先代社長等がこの合意形成に主導的な役割を果たしていただきたい。なぜなら、これまで事業・会社を経営してきた実績があるからこそ事業・会社の承継が必要なのであって、その意思や影響力は大きいからです。
この合意書には前述の除外合意・固定合意の他に、推定相続人との衡平を図るための措置や、後継者が事業・会社を承継しない場合の措置などを定めます。
(2)経済産業大臣の確認
合意書作成の日から1ヶ月以内に、経済産業大臣に合意の確認を申請します。申請窓口は中小企業庁です。
申請にあたっては、申請書や合意書の他、後継者と推定相続人全員の印鑑登録証明書、推定相続人を確認するための先代社長等の戸籍謄本など、いくつかの書類を揃えて提出します。
先代個人事業主名義の事業用資産の除外合意の場合には、認定支援機関の確認書も提出します。
先代社長の株式等の固定合意の場合には、税理士等による株式等の価額の証明書が必要です。
経済産業大臣が確認した後、「確認証明書」の交付を受けます。この書類は後で家庭裁判所に提出します。
(3)家庭裁判所の許可
経済産業大臣から確認証明書の交付を受けた時から1ヶ月以内に、家庭裁判所に合意の許可を申立てます。申立てる家庭裁判所は、先代社長等の住所地を管轄する家庭裁判所です。
※許可を求める時の事件名は「遺留分の算定に係る合意」になります。
家庭裁判所の許可が得られた時点で、この合意は完全に有効になります。
ただし、経済産業大臣の確認が取り消されたり、先代社長等より先に後継者が亡くなった場合など、合意書の効力が消滅するケースもあります。
★先代社長等の役割
先代社長等は合意形成に取り組む他に、大切な役割があります。
その役割とは、先代社長が持っている会社の株式等のすべて、あるいは先代個人事業主名義の事業用資産のすべてを、後継者に遺贈する旨の記載のある遺言書を書くことです。
仮に先代社長等が生きている間に後継者が事業・会社を承継させるために生前贈与をする計画であったとしても、まずは遺言書は作っておいた方が良いと私は思います。無事に生前贈与ですべての事業用資産を後継者に渡し終えたなら、新たに遺言書を作り直せば良いのです。
なお、生前贈与をする場合には、上記の手続きとは別に贈与税の納税猶予の手続き等をしましょう。これについての説明は別のページをご覧ください。
★行政書士がお手伝いします!
このページでご紹介した遺留分への対策で、行政書士は次の事について先代社長・後継者のお手伝いができます。
- 贈与契約書の作成
- 合意書の作成
- 経済産業大臣への確認申請と、必要書類の取得
- 戸籍謄本等の取得と法定相続情報一覧図の作成・申請・取得
- 遺留分対策とは別に行う事業承継支援制度の手続き
また、様々な事業承継制度の利用には次のような多くの専門職が関わる必要があります。必要な専門職の紹介や連絡調整も行政書士が行います。
|
認定支援機関 |
正式には「認定経営革新等支援機関」と言います。 先代個人事業主名義の事業用資産の確認書を作成してもらいます。 他の事業承継制度を利用する場合に、事業承継計画書の作成にも関わっていただきます。 |
|
税理士 |
株式等の評価証明書を作成してもらいます。 事業承継税制を利用する場合や、贈与税・相続税の申告をお願いします。 |
| 司法書士 |
遺留分の放棄、合意書の許可など家庭裁判所に提出する書類の作成をしてもらいます。 その他、不動産の名義変更の手続き、会社の役員・社長の変更登記もお願いします。 |
| 社会保険労務士 |
先代社長の会社の株式等の除外合意や固定合意を経済産業大臣に確認してもらう際に、従業員数証明書の取得をお願いすることができます。 |
言葉の説明
遺留分とは
配偶者と子※に認められている最低限度の相続分のことを遺留分と言います。
遺留分は、「法定相続分の2分の1」です。
実際に相続した価額が、遺留分に足りない場合は(このことを「遺留分の侵害」と言います)、その足りない分を、他の遺産を受け継いだ人に請求することができます。
※子が遺言者より先に死亡している場合には、その死亡した子の子、つまり遺言者の孫が相続人になります
※子も孫もいない場合には、遺言者の親が相続人になり、親にも遺留分が認められています。
※親もいない場合には、遺言者の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
一般的な遺留分の計算する際の遺産
遺留分を計算する場合には、故人が亡くなった時の財産のすべてを「遺産」として考えます。もちろん、負債も遺産に含めますが「財産額を減らすための遺産」としてです。
その他に、次の生前贈与の額も含めます。
| 相続人への贈与 | 亡くなる前の10年間にした贈与のうち、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額」のすべて |
| 相続人以外への贈与 | 亡くなる前の1年間にした贈与すべて |
※死亡保険金は原則として遺産には含めません。
推定相続人とは
Aさんの推定相続人とは、現在は生きているAさんが仮に今、急に亡くなったとした場合の法定相続人のことです。
Aさんに戸籍に記載されている配偶者がいれば、その配偶者は推定相続人の1人です。
Aさんに子供がいれば、その子供も推定相続人です。
Aさんの子供のうち亡くなった子供Bに子Cがいれば(つまりAさんの孫)、Aさんの生きている子供とCも推定相続人になります。
ではAさんに子供がいなければ?
子供のいない人の推定相続人の判断は行政書士や弁護士等の、相続を扱う専門職に任せた方が良いと思います。