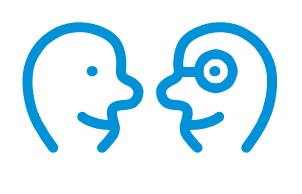個人事業の場合、事業主の能力や信用で経営が成り立っていることが多いと思います。そのため、経営を受け継いだ当初は後継者の努力にもかかわらず、売上が落ちることもあるでしょうし、仕入先からの仕入れ条件が厳しくなったりもします。
また、事業用資産も事業主個人の名義であり、その資産を受け継ぐ場合には贈与または相続によることも多いでしょう。あるいは事業主の他に資産を共有している人がいる場合には、その持分を買う必要があるかもしれません。
そのため、個人事業を継ぐ場合には、後継者の当面の事業資金が課題になることがあります。
経営承継円滑化法は、そうした事態への金融支援を定めています。
その概要をお示ししますが、具体的には金融機関か行政書士に御相談ください。
※この金融支援を御希望の場合、都道府県知事の認定が前提です。この認定申請を支援できるのは行政書士です。
Table of Contents
1.個人事業主への金融支援の内容
先代の個人事業を受け継ぐ後継者のための金融支援の種類は、次の表のようになります。
| 後継者の類型 | 受けられる金融支援の種類 |
| 個人事業主 | 〇経営を承継した後に必要となる資金の借入に対する信用保証 |
| これまで個人事業を営んでいない個人 | 〇これから他の中小企業(個人事業を含む)の経営を承継するにあたり必要となる資金の融資又は信用保証 |
個人事業主は、この経営承継円滑化法による特例を受けなくても、日本政策金融公庫等から融資を受けられます。
2.金融支援を受けるための手続
経営承継円滑化法による金融支援を希望する後継者である個人事業主等は、まず、次の表に掲げる事柄に該当することを都道府県知事に認定してもらう必要があります。
| 後継者の類型 | 認定を受ける内容 | |
| 個人事業主 |
次の(イ)又は(ロ)のどちらかに該当すること。
|
|
|
(イ) |
次のすべてに当てはまること
|
|
|
(ロ) |
次のすべてに当てはまること
|
|
| これまで個人事業を営んでいない個人 |
次のすべてに当てはまること
|
|
上の表に書いた事柄は、大まかな事柄です。
例えば、他の中小企業の資産を相続や贈与で譲り受ける場合、相続税又は贈与税を支払う必要が生じることがあります。この納税資金の融資を受ける際にも、この特例により信用保証等を受けることが可能です。
より詳細には専門家、金融機関等に御相談ください。
3.都道府県知事の認定を受けるための条件
次の①~⑦のいずれかに該当すること。あるいはその他に後継者の事業継続に支障が生じていると認められることが条件です。
① 後継者が先代の事業用資産を取得する必要がある。
この事業用資産には先代事業者が事業のための借入金や、従業員等への未払金も含みます。
そのため、金銭消費貸借契約書等の書類や先代事業者の所得税確定申告に添付した貸借対照表等の計算書類、事業用資産が不動産なら登記事項証明書を認定時に提出する必要があります。
② 後継者が相続又は贈与により取得した先代の事業用資産に関わる相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
相続税又は贈与税の申告書案などで納税額の見込みを示します。
③ 先代から事業を受け継いだ後の3カ月間の売上高等が前年同期の3か月間の売上高の100分の80以下に減少することが見込まれる事
先代事業者の合計残高試算表や青色申告決算書と、後継事業者の合計残高試算表などを元に計算します。そのため、認定を申請する時にこれらの書類が必要になります。
④ 仕入先からの仕入れに関する取引条件が、後継者にとって不利益となる設定又は変更が行われたこと。
後継者の不利益になる取引条件の変更等を行った仕入先からの仕入額が、後継者の仕入額総額の20%以上を占めている場合です。
そのため、仕入先の名称や住所の他に、仕入額等の計算書類、不利益になる変更を示す契約書や通知書又は依頼書等で証明します。
⑤ 取引先金融機関からの事業用資金の借入に関する返済方法等の借入条件の悪化、あるいは借入金額の減少、与信取引の拒絶などの支障が生じていること。
借入条件の悪化には、もちろん金利の引上げも含みます。
借入条件が悪化した金融機関からの借入金が、借入総額の20%以上であることが必要です。
先代の確定申告の根拠になった会計書類や金融機関発行の借入金の残高証明などを準備します。
⑥ 遺留分侵害額請求や先代から相続により取得した事業用資産を取得するために代償分割によることを内容とする調停や審判が確定した事
和解契約書や審判書、調停の調書等により証明します。
⑦ 事業承継税制の適用を受けるための都道府県知事の認定条件を満たすこと
詳しくは事業承継税制について御確認下さい。