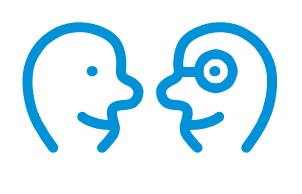集落や町内会、自治会などの、地域に住む住民で作る団体を「地縁団体」と言います。総務省の調査では、全国で約29万6千の地縁団体があるそうです。
※総務省「地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果(令和5年4月1日時点)」
ご存じのようにこうした地縁団体は、地域の道路や公園などの清掃活動や、ゴミ集積所の整備、回覧版、市町村の刊行物の配付など様々な活動を行っています。
ほとんどの活動は法人にしなくても、何の問題も無く行えます。しかし中には、法人でなければできないことや、法人の方が活動しやすいこともあります。
このページでは地縁団体を法人化するメリットについて考えてみます。
なお、地縁団体を法人にする方法については、別のページに記します。
Table of Contents
1.法人とは
日本の場合、18歳になれば自分の判断で契約もできるし、高額な買い物も自由にできます。一方で、様々な責任を負うことにもなります。
人の集まりである団体を法人にすると、その団体があたかも1人の成人のように契約の主体になり、団体名義の財産を所有することができるようになります。
例えば、友だち3人で古着の移動販売の商売を始めたとします。商売のために車を購入する場合を考えます。
法人であれば、法人名義で車を購入できます。 一方、法人にしなければ、3人の誰か1人の名義で車を購入することになるでしょう。この違いは、活動を継続していく中で大きな差になります。
法人というとピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、株式会社は法人の一種だと言えばご理解いただけるでしょうか。またNPO法人や社会福祉法人、一般社団法人などのように団体の正式名称に「法人」という言葉がついていることもあります。
集落や町内会などの地縁団体を法人化した場合には、その名称に「法人」という言葉はつかず、従来の名称で活動を継続することができます。
2.地縁団体を法人にするメリット
集落や町内会のような地縁団体を法人にすることで、いくつかのメリットがあります。
その主なもの3つについて記します。
(1)地縁団体名義の不動産を所有できる!
地縁団体を法人にする制度は平成3年にスタートしましたが、その目的は地縁団体名義の不登記が登記ができるようにするためでした。
これにより地域の集会所等を町内会や集落の名義にすることが可能になります。
私は地域内に山林や原野などがある集落や自治会が法人化することに大きなメリットがあるのではないかと考えています。
メリット1 山林等の相続手続が楽になる!
故人の遺産に山林や原野などが含まれている時、相続人がその山林等を所有したくないと思うことがあります。
この場合、「相続土地国庫帰属制度」を利用し国に引き取ってもらうことが可能です。しかし、山林でこの制度を利用しようとすると相続人の費用負担が大きくなる可能性が高いです。また、国に引き取ってもらうためにはいくつかの条件を満たした山林でなければならないため、条件に合わなければ国は引き取りません。
その結果、相続人が山林を放置することもあり得ます。
もし集落が法人になっていれば、その相続人から山林を寄付してもらえるかもしれません。「処分に困る山林を引き取ってくれるなら、タダでも良い」と考える人は結構います。あるいは、遺言に書いておいてもらうことも考えられます。
<不動産登記の特例>
自治会等が事実上所有しているけれど、登記簿上の名義は複数の地域住民で共有している不動産があり、この不動産を自治会等の名義にする場合。
通常の手続きでは登記簿に記載されている共有者が死亡しているならば、まず、その死亡した共有者の相続人の名義にし、その相続人から不動産を譲渡してもらうという段取りになります。
ただ現実には登記簿記載の共有者が死亡しても、相続登記をしていないケースが多くあります。その結果、亡くなった共有者の相続人も死亡し、新たな相続が発生し相続人が何十人にもなっているのです。中には連絡先がわからない相続人がいる場合もあります。
集落が法人化していると、こうしたケースでも登記の特例を利用し、山林を集落名義にすることができるかもしれません。
地縁団体所有の不動産登記の特例については、「地縁団体の不動産取得と登記」にお示しします。
地方自治法第260条の46
メリット2 山林等のある景観や利益を保存しやすくなる!
近年、太陽光発電や風力発電設備の設置をめぐり、地域住民が景観の破壊や防災を心配して反対するという事例が発生しています。
水源や防災や景観など、地域の人々にとって大切な不動産が開発の対象にならないように、あらかじめ不動産を集落名義にしておくことも保存方法としては考えられるのではないかと私は思います。
もちろん、保存するための集落としての負担も考える必要はありますが...。
(2)不動産以外の物も地縁団体名義で所有できる!
例えば、防災・減災に必要な機材や備蓄倉庫。あるいは自動車。こうした物も町内会等の名義で所有できるようになります。
公共交通機関が不便な地域で、地縁団体名義の自動車があれば。もしかすると、その自動車を住民の足として、あるいは高齢者・障がい者等の生活支援などに利用できるかもしれません。
実際に利用できるかどうか、利用できるとしてもどのような規定等が必要なのか等、検討する必要があると思いますが...。
(3)地縁団体が契約の当事者になれる!
地縁団体を法人にできる制度は、先に記したように地縁団体名義の不動産の登記ができるようにするためでした。
そこから町内会や自治会の多様な活動を後押しするため、令和3年の地方自治法改正で地縁団体が契約の主体となれるようになりました。
これにより新たに法人を作らなくても、例えば地域住民のために食料・日用品を販売したり、地縁団体名義の山林から山菜やキノコをとって特産品として販売したり、地域のための水道事業や発電事業が地縁団体としてやれるようになります。
市町村等の事業を地縁団体が法人として受託したり、補助金・助成金も受けやすくなるでしょう。
地縁団体名義の預貯金口座を開設することも可能です。これにより団体代表者や会計責任者個人の口座と明確に区別して管理できるようになるのは、法人化の大きなメリットの1つです。
3.法人にした場合に気をつけたいこと
町内会や自治会の多くは、法人にしなくても毎年定期総会を開いたり、役員会等も定期的に行い、そこで何を決議したのか等の記録を残し、会計帳簿を監事が確認していることでしょう。
地縁団体を法人にした場合、これらのことを法の定めに基づいて行うようになります。
地縁団体の法人化は、市町村の認可によって行います。ということは、従来よりも作成し保存する書類が増えるかもしれませんし、その様式にも気を配る必要が生じるでしょう。
また、収益事業を行う場合には法人税・消費税などの税の申告・納税の可能性もあります。
地縁団体が法人化することのメリットは大きいと考えていますが、こうした負担とのバランスを考えることは大切です。