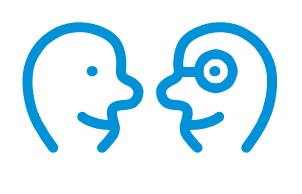家族が入院するときや老人ホームなどに入所するとき、「身元保証人」を求められたことはありませんか?

「身元保証人」ではなく、「保証人」とか「身元引受人」などと言われたかもしれませんが、この記事では「身元保証人」と記します。
まわりに身元保証人を引き受けてくれそうな人がいないとき、困っちゃいますよね?
でも、そもそも身元保証人には何を求められているのでしょうか?
この記事では身元保証人について考えてみます。
※この身元保証人は、就職の時に就職先から求められる「身元保証人」とは異なります。
Table of Contents
1.病院や老人ホーム等は、なぜ身元保証人を求めるの?
令和4年に総務省の関東管区行政評価局が行った病院や施設を対象にした調査をもとにして考えると、身寄りのない方の入院や入所には次のような心配が病院・施設にあるようです。
- 入院費・入居費の支払いが滞る事が少なくない。
- 治療や介護の計画へのご本人の意思がわからない。
- 死亡した場合の遺体や遺品の引き取り等への対応が困難。
- 次の受け入れ先等を探すのが困難になる。
- 入院・入居中に起こる出来事への対応で、後で訴訟に結び付くのを避けたい。
また、病院も施設も人手が不足してるため、職員の負担が増えることは極力避けたいという想いもあるのです。
おそらくはそのために、身寄りのない人だけでなく入院や入所する全ての人に、身元保証人を求める対応が一般的になったのだと思われます。
身元保証人がいないと、入院も施設に入居することもできない?
医療や介護に関わる制度を管轄する厚生労働省は、「身元保証人がいない人」の入院や入居について、どのような対応をしているのでしょうか?
法制度上、病院や介護事業者は「正当な理由」があれば、入院やサービス提供を拒否できます。
でも、厚生労働省は平成30年に都道府県の病院を監督する部署に次のような通知を出しています。
「身元保証人がいないことだけを理由に入院を拒否することは『正当な理由』にはならない」
特別養護老人ホームや老健についても、同じ年に同じような通知を出しています。
特養や老健以外の介護事業者について同じような通知を出しているかは私は調べられませんでしたが、厚労省が定める様々な介護事業の基準には「正当な理由がなければサービス提供を拒否できない」ということは書かれています。
それでも、令和3年から令和4年にかけて関東管区行政評価局が行った調査では、身元保証人がいない人の入院・入居を拒否している病院や施設があることがわかりました。
それはやはり、身元保証人がいない人の入院・入居後の対応が、病院や施設にとってはそれほど大きな負担になるからでしょう。
また、介護保険の指定を受けていない老人ホーム(例えばケアハウスやサ高住にはそのような施設もあると思います)は、上記のような厚労省の通知は出ていないようです。ということは、「老人ホームは身元保証人を求めるもの」と考えた方が良いでしょう。
そうであるならば、身元保証人になってくれそうな人がいない人は、何らかの手立てを準備しておくことが必要になるのではないでしょうか?
2.身元保証人の役割
そもそも病院や施設が求める「身元保証人の役割」は何なのでしょうか?
厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」では、身元保証人の役割を次の6つに分類しています。
① 緊急時の連絡先
入院・入所の後に容態が急変した場合、その後の対応についての相談先としての役割を求められます。
身元保証人が親族以外の人だったり、親や子あるいは兄弟姉妹以外の場合には、身元保証人に本人のご家族に連絡をとってもらうこともあるかもしれません。
② 入院計画書(介護施設の場合はケアプラン)に関すること
例えば「手術をするか?」とか「予防接種を受ける?受けない?」というような医療に関わる判断は基本的には御本人の意思が重要です。また、ケアプランをケアマネージャーが説明したり、ご本人の希望を聞く場合に、ご本人に意思を伝える能力や判断力が必要になる場合もあります。
もしご本人が自分の意思を表現できなかったり、説明しても理解する力や判断する力が非常に弱くなっている場合に、ご本人と一緒に、あるいは代わりに説明を聞き、治療方針やケアプランについて同意を求められることがあります。
※成年後見人等は医療同意はできないので、あらかじめ対応を考えておく必要があります。
③ 入院・入居中に必要な物品の準備に関すること
例えばオムツ。洗面用具や下着など。入院・入居中に必要になる物品は意外に多いものです。
病院内で買えるもの等もありますが、その「買う」あるいは「レンタルする」という決定をし、その費用を支払う役割をする人が必要になります。
もちろん、病院・施設内で賄えない物は、外で買って届ける必要も生じます。
④ 入院・入居費用に関すること
身元保証人に求められる大きな役割の1つです。
立替払いをしてもらえる人がいないならば、あらかじめ、その費用分の金額と支払方法を準備しておく必要があります。
⑤ 退院等に関すること
最近の病院は入院期間が短く、症状が安定したら退院又は転院を求められることがあります。
施設に入居している場合には、施設によっては「介護が必要になったら退去してもらう」とか「●●はできるけれど、▲▲は対応できない」ということで他の施設に移る必要が生じることがあります。
その際に、その退院や転居に関わる手続を誰がするのか?ということが問題になります。
これについては病院や施設は、退院後・施設退去後の受け入れ先の候補を見つける手伝いはしてくれるかもしれませんが、転院先・転居先の手続自体は行えません。
⑥ (死亡時の)遺体・遺品の引き取り・葬儀等に関すること
これが「入院・入居の費用の支払い」と並んで、身元保証人が求められる大きな理由です。
全く身寄りがなく、法定後見人もついていない場合には、最終的には市区町村が対応します。(市区町村が入居している施設に委託することもあります)
しかし、その事務に関する負担は大きく、また遺品等の私物は気楽に処分できるものでもないので、病院や施設だけでなく市区町村でも対応に苦労することになります。
そのため、この遺体・遺品の引き取りや葬儀に関することについて身元保証人への期待は大きいと言えます。
3.親族に「身元保証人になってください」とお願いするとき
親や子、兄弟姉妹だけでなく、甥姪や、従兄弟姉妹に身元保証をお願いする場面が、将来、あなたにも訪れるかもしれません。
そうした時に、安心して身元保証人になってもらえるように、あらかじめ準備しておいた方が良いことがあります。以下、4つの準備について記します。
(1)医療、特に延命治療についての希望を書いておく。
あなたの意識が無い時。特に「もはや手の施しようがなく、延命治療を行わなければ死亡する」という状態になった時。
親族に延命治療をするか否かの判断を求められます。
この判断は非常に重く、親族の心の負担になることが多いです。
ですから、あらかじめ延命治療への希望を文書にしておきましょう。また、それに合わせて口頭でも自分の気持ちを伝えておきましょう。
伝える相手は身元保証をお願いする人の他、危篤の時に病院に来てくれそうな人すべてに伝えておいた方が良いと思います。
そうした親族がいない方は、支援者や主治医、ケアマネージャーなどに書面を託しておきましょう。
(2)亡くなった時の対応
亡くなった時以降、病院・施設から遺体・遺品の引き取り、死亡診断書の受取りや死亡届の提出その他の様々な手続が始まります。
その最初の対応については葬祭業者が支援してくれます。(相続手続は別です)
ですから、生前に葬祭業者を見つけ契約等をしておき、親族等に葬祭業者の連絡先を伝えておくと良いでしょう。
(3)支払いへの対応
身元保証人の大きな役割は、本人が何らかの事情により病院等に費用等の支払いが出来ない場合に、代わって支払い手続きをすることです。
そもそも本人にお金がないなら、事前に生活保護等の手立てをしておくべきです。
でも入院費等に充てる位のお金があるのであれば、そのことをあらかじめ身元保証人をお願いする親族に伝えておいた方がよいでしょう。また、病院・施設への支払い方法も打合せておけば、親族は安心して身元保証人になってくれるのではないでしょうか?
その支払方法については、いろんな手段があります。専門家に相談すれば安全な方法を教えてくれるはずです。
(4)緊急入院時の持出グッズの準備
事故や突然の病気などで緊急入院をする時に、マイナンバーカードや資格確認書の保管場所を親族等に持ってきてもらう必要があるかもしれません。
また、当面の入院に必要な洗面用具や下着類なども、持出カバンに入れて準備しておけば「カバン持ってきて」の一言で支援してもらえます。
4.身元保証をする事業者に依頼するとき
近頃は身元保証を行う会社や一般社団法人・公益社団法人などが数多く存在します。
ですから、そうしたサービスを利用するのも選択肢の一つと言えるかもしれません。
ただ、身元保証サービスを契約する際には、一定の金額を一括で支払わなければならないケースが多いため、契約前に慎重に検討し、納得してから契約しましょう。
(1)事業者の説明を聞く時に同席してくれる人はいますか?
身元保証サービスは、複雑でわかりにくい言葉が使われていることもあります。
ですから、事業者からサービスや契約書の内容を聞く場合には、誰かに同席してもらった方が良いと思います。
(2)サービスや契約内容などのチェック
身元保証会社等が提供するサービスや提供方法は多種多様です。それでも、少なくとも次の点については事業者に確認し、納得してから契約するようにしましょう。
- サービスの内容とサービス開始の時期
- 必要書類(契約書の種類と作成方法や時期など)
- 料金や費用の支払金額・支払方法・支払の時期
- 契約者(ご自身のこと)の権利と義務
- 前もって事業者に預ける身元保証に関わる金銭の保管方法
- 事業者が倒産その他の理由でサービス提供できなくなった場合に支払済みの金銭の扱い
- 解約の方法 と 支払済みの金銭の扱い
5.身元保証の事業者以外のサービスを利用する方法
身元保証を事業としている業者以外に、弁護士や行政書士、司法書士等の士業に依頼する方法があります。
任意後見契約と死後事務委任契約を中心にした契約の締結です。
この契約が締結されている事(死後事務委任契約の場合は公正証書で契約書を作成している事)で、身元保証人が不要になる場合もあります。
料金はその事務所によって異なりますが、一度、相談されてみてはいかがでしょうか?
また現在、政府は身寄りがなく、民間のサービスを利用するだけの金銭を準備するのが難しい方を対象とした制度を準備しているところです。「いつ制度を利用できるのか」という問題はありますが、今現在、健康に不安がない60代前半の方であれば、その制度の全容が明らかになるのを待ってみるのもアリかもしれません。
相談先
身元保証人を引き受けてくれそうな親族がいない方はもちろんですが、親族が安心して身元保証人になれる方法で悩んでいる方は、早めに、つまり元気なうちに専門家に相談しましょう。
その相談をする専門家は、成年後見を業務にしている人が良いでしょう。
相談料は、1時間くらいの相談で5千円~1万円(税別)位かと思います。中には初回相談を無料にしている事務所もあります。
また、各地でセミナーや相談会も実施されているので、そうしたイベントに参加して専門家の品定めをするのも良いと思います。
専門家を上手に利用してください。
なお、当事務所へのお問合せは 、電話なら
022-796-5845
※出来る限り月・水・金の9:00~17:00にお電話ください。
※上の時間外の場合や、時間内でも電話に出れないこともあります。その時は留守番電話に録音してください。こちらから2営業日以内に折り返し御連絡いたします(連休の場合は少し時間がかかります)。
メールなら、次のQRコードを読み取るか、下のアドレスに御連絡下さい。3営業日以内に返信いたします(連休の場合は少し時間がかかります)

メールアドレス ⇒ gyo.sawa55@outlook.jp
※当事務所からの返信メールが、お客様の「迷惑メール・フォルダ」に入っていることがございます。
問い合わせ後に当事務所からの返信が届かない場合、念のため迷惑フォルダをご確認くださいますようお願いいたします。
参考資料
この記事は、主として次の4つの資料を参考にしています。
①身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査(結果報告書)
・・・令和5年8月 総務省行政評価局
②高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機) -入院、入所の支援事例を中心として-(結果報告書)
・・・令和4年3月関東管区行政評価局
③平成29年度老人保健事業推進費等補助金「介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業報告書」
・・・平成30年3月みずほ情報総研株式会社
④身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
・・・厚生労働省