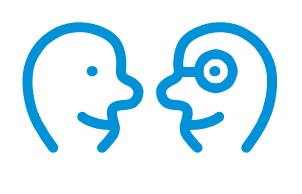親族を亡くした労働者が仕事を休む時、忌引休暇とか慶弔休暇を取得してお葬式をあげたり、故人に関わる手続の見通しをたてたりします。
けれど、もし、あなたが故人の葬儀の他に遺品整理や相続手続などを行うとすれば、忌引休暇だけで見通しをつけることが可能でしょうか?
この記事では、そんなことを考えてみます。
Table of Contents
遺族の忌引休暇(慶弔休暇)の日数
人事院の規則を見てみると、国家公務員の忌引休暇は下の表のようになります。
※人事院=国家公務員の採用・働き方・給与等を担当する役所
※国家公務員の場合は、忌引休暇とは言わずに特別休暇と言うようです
| 亡くなった方 | 忌引休暇の日数 |
|---|---|
| 配偶者、父母 | 7日 |
| 子 | 5日 |
| 祖父母 | 3日(事情により7日) |
| 配偶者の父母 | 3日(生計を同じくしていた場合は7日) |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ、おば | 1日(事情により7日) |
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
民間企業の場合には、忌引休暇(又は慶弔休暇など)は就業規則などで規定しているかと思いますが、中には規定がない企業も10%程度あるそうです。
忌引休暇を規定している企業であっても、非正規雇用の従業員にも適用しているところは50%程度。ということは多くの非正規雇用の従業員は、親族が亡くなった場合には有給休暇を利用するか、それ以外の方法で対応しているということなのでしょう。
※「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」独立行政法人労働政策研究・研修機構(平成30年7月24日)を基にしています。
※非正規雇用=パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員等
ここで注意していただきたい事があります。
超高齢社会という現実
日本は総人口の30%が65歳以上だそうです。つまり世界に例を見ない超高齢社会。
そして子どもが少ない。出生率も低いまま。
最近、「人手不足」という言葉が実態を伴って、あちこちで見られるようになってきたと思いませんか?
様々なことに人の支援が必要な高齢者が増えてきているのに、支える人が不足している。それは福祉や医療に関わる人だけでなく、高齢者の若い親族も少ないということでもあります。
その延長線上に高齢者の死があり、その死に伴う様々な手続がある。
近頃は、自分の親や配偶者の親の死後の対応だけでなく、兄弟姉妹・おじおば等の死亡に対応している方も増えているような気がするのは私だけでしょうか?
そうすると、「忌引休暇の他に、仕事をしながら死後の手続をしているうちに、他の親族が亡くなった」という事態が生じるかもしれませんね
人が亡くなった後の主な手続
では、人が亡くなった後、どのような手続があるのでしょうか?
その主なものの内、期限が法律で定められているものを下の表にまとめました。
| 亡くなってからの期限 | 手続 | 備考 |
|---|---|---|
| 直後 | 死亡診断書(又は死体検案書) | |
| 7日以内 | 死亡届(火葬許可申請) | 市区町村役場 |
| 14日以内 | ・健康保険又は後期高齢者医療保険資格喪失届 ・介護保険被保険者証の返却等 ・年金受給権者死亡届等 | ・年金事務所への死亡届は、マイナンバーを事前に届けていれば不要 |
| 3カ月以内 | 相続放棄又は限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 所得税の準確定申告 | 税務署(必要な方) |
| 10カ月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記 | 法務局 |
もちろん、葬儀・法要や納骨等も重要です。故人の生前の人付き合い等によっては、葬儀等の後もお悔やみにいらっしゃる方もあるかもしれません。
また、他に、預貯金等の相続手続や、遺品整理・処分も加わります。
相続手続の中には、「故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式」が必要になるものが多いです。その中で「故人の死亡の事実が記載されている戸籍」は、死亡届を提出してから1週間から10日程度しないと交付してもらえません。
ですから、遺族が「忌引休暇中に必要な手続の中でやれるものをやっておく」というご希望がある場合でも、この「故人の死亡の事実が記載されている戸籍」が忌引休暇中には入手できないため、どうしても有給休暇等を利用せざるを得ないか、専門職に手続きを依頼する必要が生じます。
死亡保険金の請求
多くの死亡後の手続には「死亡の事実が記載されている戸籍」が必要になるのですが、死亡保険金の請求は「死亡診断書」があれば手続可能です。
そのため死亡保険金は、葬儀等の支払いなど故人逝去後に早く支払う必要な費用に充てるのに効果的です。
死後の事がらへの対策
短い忌引休暇の間で、故人に関わる手続をすべて終えることは、もちろん不可能です。それどころか、「今後の段取りをつける」「見通しを立てる」ことすらも、難しいです。
ほとんどの人の死は不意に訪れ、残された者は戸惑いと喪失感の中、これまであまり経験したことのない環境や手続の嵐の中に放り込まれるからです。
だからこそ、 亡くなった後、親族が故人の供養や服喪に専念でき、また自身の日常に早期に戻れるようにするには、高齢者の生前の対策=終活が重要なのです。
特に次の3つは、財産や親族の有無に関わらず、ほとんどの高齢者に準備してほしいと私は思います。
- 遺言
- 死後事務委任契約
- 物や契約等の整理
もちろん、人によって具体的な中身は変わると思いますが、キーワードとして覚えてもらい、終活の道しるべとしてしてもらいたいのです。
詳しい説明は他の記事を御覧ください。