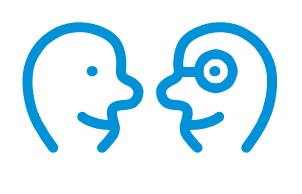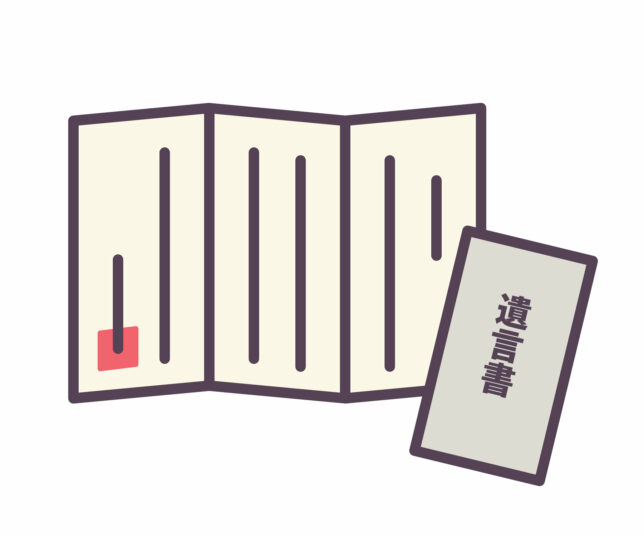
テレビや新聞で、「遺言のデジタル化」に関わるニュースを御覧になった方も多いのではないでしょうか?
私が目にしたニュースの中には「遺言が作りやすくなる!」「遺言作成のハードルが下がる」と評価するものもありました。
確かに、遺言のデジタル化、つまりパソコンやスマートフォン等を利用して遺言が作れるようになれば、 インターネット等で書き方を参考にしてパソコンで遺言書を作ったり、本人が遺言の内容を語る様子を録画すれば、誰でも簡単に遺言がつくれそうな感じを受けます。
では遺言がデジタル化されれば、弁護士や行政書士などの専門家の支援なしに、誰でも簡単に遺言を作れるようになるのでしょうか?
Table of Contents
1.遺言のデジタル化とは?
この記事で言う遺言のデジタル化とは、次の2つの事を指しています。
- 公正証書遺言のデジタル化
- 自筆証書遺言のデジタル化
この2つを分けて簡単に説明します。
(1)公正証書遺言のデジタル化
令和7年10月1日から公正証書の作成について、大きく次の3つの変更がされます。
※ただし、指定公証人の役場でだけ利用可能で、宮城県内の公証役場は令和7年11月17日から利用可能になるようです。(予定)
- インターネットのメールを利用した嘱託が可能。
- 公証役場に行かず、ウエブ会議を利用した公正証書の作成が可能。
- 公正証書は原則として電子データで作成・保存し、押印はせずに電子サインだけになる。
※電子サイン=タッチディスプレイに電子ペンで氏名を手書きすること。
上記の内、遺言作成については2と3が重要だと思います。
ウエブ会議を利用して公正証書遺言が作れる
例えば「車椅子を利用していて、公証役場に行くのが困難」という方の場合、これまでは公証人に遺言者のいる場所に出張してもらっていました。出張にかかる料金が加算されるので、遺言者の負担は増えることになります。
今後は、「公証人に出張してもらう」他に、「Web会議を利用して遺言書を作る」という選択肢が増えたということです。
ただし、Web会議ができる環境の他、電子サインができるパソコン・タッチディスプレイを準備する必要があります。
公正証書は電子データで作成・保存し、署名・押印の代わりに電子サインをする
これまで公正証書遺言は紙で作成し、遺言者や証人が原本に署名し押印していました。特に遺言者は実印で押印する必要がありました。
今後は公正証書遺言の原本は電子データで作成されることになり、遺言者や証人は押印はせずに電子サインをすることになります。
また、公正証書遺言が完成した後、原本と同じ内容を印刷し綴じられた正本と謄本を遺言者は受け取って帰っていましたが、今後は、その他に電子データで受取る方法も選択できます。
電子データで受取る方法は、メールを通して受取る方法と、自前のUSB等で受取る方法が選択できるようです。
(2)自筆証書遺言のデジタル化
「自筆証書遺言のデジタル化」とタイトルに書きましたが、正確には少し違います。
また、現在、法務省が制度改正の議論をしている最中であり、令和7年10月の現時点では、確定したものではありません。
自筆証書遺言は現在は「本文は全て自筆で、正確な日付と本人の署名と押印が必要」で、本文につける財産目録等は「原本のコピーやパソコンで作成したものを印刷し、本人の署名と押印」でOKという作り方です。
今、法務省で議論されているのは、この自筆証書遺言の他に、デジタルで作成する方法が加わるのです。
デジタルで作成する方法は、パソコンやスマートフォン等で文字情報として遺言を作成するのが基本になりそうです。その上で、主として次の2つの方法が検討されています。
- 本人が文字情報にした遺言を朗読し、その様子を録画・録音する。
- 文字情報としての遺言を、公的機関に保管してもらう。保管申請の際に本人が遺言を朗読する。
上記の1は、さらに「証人の立会いのもとに朗読」する方法と「証人は不要とし他の措置をとる」方法に分けて議論されています。
また、2についても、保管してもらうのは「電子情報」なのか、「印刷した書面」なのかに分かれます。ちなみに、2の場合は家庭裁判所の検認は不要(つまり自筆証書保管制度と同じ)とするようです。
2.デジタル化後にも当てはまる遺言作成時に気を付けたいポイント
1を御覧になって気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、変わるのは「遺言の作り方」だけです。その他のことは現在と同じです。
たしかに自筆証書遺言で本文を全て手書きするよりは、パソコンで作成できた方が楽です。書き間違いを見つけた時に修正しやすいというのは、気分的にとても楽になります。そもそも、他人にパソコンで文字データを作成してもらうことだって可能になります。
けれど、遺言では「作り方」以上に気を付けたいポイントがあります。
- 遺言が本人の意思を表している事。
- 誰が読んでも本人の意思の解釈に違いが出ないようにすること。
- 遺産や人等が特定できること。
- 他の法律等に抵触する内容でないこと。
- 税負担等への考慮もされていること。
- 遺留分への対応、その他、相続人や受遺者が受け入れやすい内容であること。
- 遺言者の指定など、遺言の実現への配慮、相続人の負担軽減につながること。
- 最終的に引き受け手がない遺産・遺品が生じないようにしていること。
上のポイントについて、ここでは詳しくは説明しません。でもいずれも、遺言を作成する時に検討しておきたいポイントではあります。もちろん、全てのポイントについて配慮の行き届いた完ぺきに近い遺言は、場合によってはできないかもしれませんが、それでも検討だけはしたい事がらではあります。
そのためには、相続に関する広範な知識などが必要になります。
それらは、果たしてインターネットで簡単に調べられることなのでしょうか?
3.遺言のデジタル化後、専門家の支援なしで遺言書は作成できる?

ここまでお読みいただいたように、遺言のデジタル化で、確かに遺言の作り方自体は、従来よりも楽になりそうです。
ですが、肝心の遺言の内容については、そうとも言えないのではないかと私は思います。
それどころか、簡単に遺言が作れるようなるが故に、トラブルにつながる遺言が増えてしまうのではないかという懸念もあります。
したがって、「遺言を作ろう」と思いついた方は、一度は行政書士等の専門家に相談だけはした方が良いということに、今後も変わりはなさそうです。